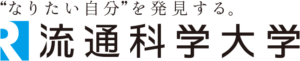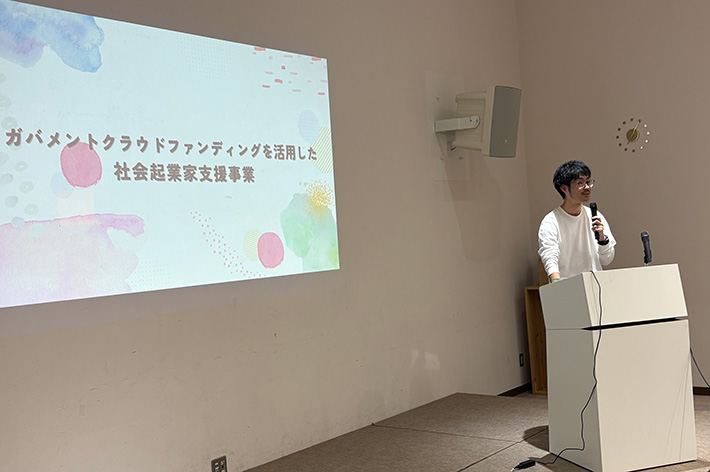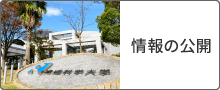全教員対象の『FD研修会』で考える。変化の激しい社会に対応できる人材の育て方
公開日:2025年10月7日

“学びの質”改革に挑む。全教員対象の研修を実施
本学では、時代と社会のニーズに即した質の高い大学教育実現の一環として、FD活動(授業をより良くするための大学の組織的な取り組み。Faculty Developmentの略)に取り組んでいます。
全教員が研鑽を積むべきテーマの研修を、高等教育推進センターが企画・実施。
今年度も“グループワーク”を活発に展開して、全4回に渡って行う予定です。
第1回 出口(DP)を意識したカリキュラム・マネジメント
目的・方法・評価の最適解を探る
『出口(DP)を意識したカリキュラム・マネジメント』について考えた第1回。
目的・方法・評価を三位一体と捉え、
- 4年進級時に学生が身につけておくべき具体的な能力は何か
- その能力をどのような方法で育成するのか
- その能力の育成、能力の熟達をどのように評価するか
の3つのテーマについて、『ラウンド・ロビン(※1)』と呼ばれるブレインストーミング技法を用いて、個人ワークとグループワークを実施しました。
(※1) 簡易的なブレインストーミング技法。考えやアイデアを量的にアウトプットする(生み出す)ことを目的とするため、グループ全員に発言の機会が与えられる
第2回 教育(学び)の質保証に向けた授業方法の再検討
「(教員が)何を教えたか」から「(学生が)何を学び、身につけたか」へ

そして、この日の第2回では『教育(学び)の質保証に向けた授業方法の再検討』をテーマに、具体的な“方法論”について議論を行うことに。
高等教育では、教育の質保証を実現するために「(教員が)何を教えたか」から「(学生が)何を学び、何を身につけたか」への転換が求められています。
また、変化の激しい社会を生き抜き、答えのない問題に対応できる力の育成が社会全体で求められている今、『知識を知恵に転換することができる論理的思考力を持った人材』(本学DPのひとつ)を、どのような授業方法・教育方法によって育成するのか?
『知識構成型ジグソー法(※2) 』を用いて考えました。
(※2) 協調学習の手法のひとつ。ある問いに対し、複数の視点から書かれた資料をグループに分かれて読み、その後、他グループの人と共有し合うプロセスを経て、理解を深めるもの
知識を知恵に。論理的思考力を持った人材の育成へ


まず、個人ワークとして、思いつく限りの授業および教育方法を列挙。
その後、グループワーク、他グループとの情報交換・共有・統合を経て、『問いに対する答えと理由』を発表。
それを踏まえ、改めて教員一人ひとりが“問い”に対する答えと向き合いました。
また、グループワークの時間には、『学習におけるAIの活用』も話題に。
教員間でさまざまな意見が交わされるなど、活発な議論が繰り広げられていました。
第3回 「大学教育の質保証」に向けた学修成果・教育成果の把握と可視化

第3回となったこの日は、『「大学教育の質保証」に向けた学修成果・教育成果の把握と可視化について』をテーマに、個人ワークおよびグループディスカッションを行いました。
学生一人ひとりが身につけた資質・能力を自覚できるように
冒頭、学修成果・教育成果の把握と可視化について、「学習者本位の教育の観点から、一人ひとりの学生が自らの学修成果として身につけた資質・能力を自覚できるようにすることが重要である」としたうえで、以下の必要性について説きました。
- 教育改善につなげるためにも適切に把握・可視化すること
- 可視化に当たってはエビデンスとともに説明できるよう複数の情報を組み合わせた多次元的な形で行うこと
- その際の前提として、成績評価の信頼性を確保すること


学修成果・教育成果の把握と可視化の『意義』と『課題』
一方で、「すべてを網羅的に把握することは難しく、把握したすべてが必ずしも可視化できるわけではない」と、学修成果・教育成果の把握と可視化には限界があることを確認したうえで、評価することの「意義」と「課題」について考えました。
それらを踏まえ、「適切な評価手法を選択し、学生の学びと成長を適切に評価することができる」ことを第4回FD研修会の目標として、グループディスカッションを行いました。
正確・適切・高い信頼性のある評価の糸口を探る
前回同様ジグソー法を活用し、まず各々が立てた「問い」に対して個人で向き合った後、グループで『教育活動の前・中・後で行う評価』をーテーマに意見交換。「より正確に、より適切に、より高い信頼性を持って」評価するための糸口を探していきました。続いて、評価の選択肢を増やすことを目的に、隣り合ったグループでクロストーク。最後に、改めて教員一人ひとりが個々で立てた『問い』に対する答えを導き出していきました。
第4回 大学入学者減少時代における、本学が存続するために今しなければならない教育改善

今年度最終回となった第4回では、「大学入学者減少時代における、本学が存続するために今しなければならない教育改善」をテーマに議論しました。
「教育の質」が問われる時代へ
2028年、本学は「教育の質」に基づく新たな第三者評価(認証評価)を受けることになっています。この認証評価には新たな評価制度の導入が検討されており、学生が在学中にどれくらい力を伸ばすことができたか、成長したかをもとに「教育の質」を数段階で測られるもので、偏差値では測れない大学の「教育の質」が問われることになっています。
教員同士のディスカッションから改善のヒントを
今回のFD研修会では、このような背景を踏まえ、「内部質保証」と「外部質保証」の両面から「教育の質」を継続的に見直し、改善していくPDCAサイクルの十分な機能が必要があることを教員間で共有。本学における「教育の質」について改めて考える機会とし、以下の2つのテーマについて、教員同士でグループディスカッションを行いました。
- 授業改善アンケート含む各種アンケート調査結果から明らかになる、本学の学部教育の「現状」や「課題」
- 今後、具体的にどのような定性的・定量的評価を行えば、教員の自主的な教育改善に活用できるか

本年度のFD研修では「教育の質保証」を共通のテーマとして掲げ、4回にわたり教員間で活発なディスカッションを重ねてきました。
研修を通じて得られた議論や成果は、今後の授業づくりや学生支援に生かしていきます。
本学ではこれからも、社会の変化に柔軟に対応しながら、教育の質を高める取り組みを進めてまいります。