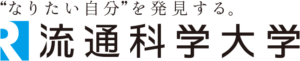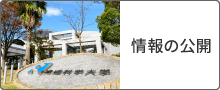行事継承と地域活性化をテーマに、『社会調査演習Ⅰ』で神戸市西部の地蔵盆・地蔵祭を調査
公開日:2025年9月2日

人間社会学部心理社会学科・栗田真樹教授と桑原桃音准教授が担当する『社会調査演習Ⅰ・Ⅱ』では、授業の一環として社会調査を実施しています。
調査方法の手順・技法を実践的に修得
同科目は3年生から履修することができ、人々の消費の場であり生活空間でもある商店街で執り行われる催事、特に『地蔵盆・地蔵祭』を対象に社会調査を行うもの。催事の実施、継続方法や諸問題に関する調査を行い、社会調査を立案・実践する力を身につけ、一連の調査方法の手順・技法を実践的に修得することを目的としています。
『地蔵盆・地蔵祭』を対象に社会調査を実施
今年度も、『神戸市西部地域の地蔵盆・地蔵祭の可能性から考える行事継承と地域活性化の要素』をテーマに、栗田教授は長田区、桑原准教授は須磨区に分かれて社会調査を実施しました。
8月18日(月)・19日(火) 須磨寺駅前商店街地蔵盆調査(準備参与観察・インタビュー調査)

8月18日(月)に『須磨寺駅前地蔵尊地蔵盆』の、翌19日(火)には『浄福寺(頼政薬師寺)地蔵盆』の準備のお手伝いに、本科目を受講する学生が参加しました。
提灯や配布するお菓子の準備をサポート
18日(月)には、学生1名が須磨寺駅前地蔵盆の準備に参加。駅前を彩る紅白の提灯の吊り下げなどを手伝いました。

翌19日(火)には、もう1名が参加。この学生は昨年度の社会調査演習の受講生。後輩へのアドバイスと、本授業での調査をさらに発展させて卒業論文を書くために参加したそう。この2名で『浄福寺(頼政薬師寺)地蔵盆』の準備のお手伝いを行いました。学生たちが手伝ったのは、子どもたちに渡すお菓子の用意。用意された数種類の駄菓子を、ひとつずつ小袋に入れていくため、入れ間違えたり、入れ忘れたりがないよう、集中して取り組んでいた2人。地蔵盆の主催者の方々と協力しながら、500人分のお菓子を用意しました。
実践から学ぶインタビュー調査の手法

お菓子の準備が終わった後は、皆さんにインタビュー調査を実施。
「今までに地蔵盆をやめるという話はあったか」「子どもたちに参拝の仕方を教えることはあるか」「なくなっていく地蔵盆と続いている地蔵盆の違いは?」「今後も地蔵盆を続けていくために取り組んでいることは?」など、それぞれが調査テーマに添った質問を次々にしていました。
終了後には、桑原准教授から学生たちのインタビューについて指摘が。限られた時間のなかで必要な情報を引き出すためにはどうしたらいいのか、アドバイスする場面も見られました。
地蔵盆運営者へのインタビューで見えた“継続”の理由
昼食後は、『須磨寺駅前地蔵尊地蔵盆』運営者へのインタビュー調査へ。
この日、学生たちがインタビューを行ったのは、前運営者である小坂さんと現運営者の片山さん。
片山さんや、長い間、地蔵盆と関わってきた小坂さんに、「主催する楽しみ」「須磨寺商店街における地蔵尊の存在」「現運営者への継承の経緯」について質問を重ねていく学生たち。なかには、「地蔵盆の参加者のなかには、お菓子をもらうためだけにくる人もいると思うが、それについてどう思うか」といった突っ込んだ質問も。

4年前まで数十年に渡り須磨寺駅前地蔵盆を主催されてきたというだけあって、今年90歳を迎えられるとは思えない歯切れの良さで、一つひとつの質問に明瞭に答えられていた小坂さん。
学生たちは、2時間にわたるインタビュー調査を通して、少しずつ変化しながら継続されてきた『須磨寺駅前地蔵尊地蔵盆』について学ぶことができたようです。
8月23日(土) 『須磨寺駅前地蔵尊地蔵盆』にて本調査

地蔵盆当日となった8月23日(土)。学生2名が『須磨寺駅前地蔵尊地蔵盆』にて本調査に臨みました。
地蔵尊前には地域の子どもたちの長蛇の列が
18日(月)に学生1名がお手伝いした紅白の提灯が所狭しと飾りつけられた、山陽電車・須磨寺駅前。15時の地蔵盆のスタートより1時間も前から、続々と子どもたちや親子連れの姿が。14時半からのお坊さんの読経が終わるころには、駅前には長蛇の列ができていました。
列に並ぶ保護者の方々にアンケート調査を依頼
そして地蔵盆がスタートすると、1名は地蔵尊でのお参りを終えた子どもたちにお菓子を手渡すお手伝い。もう1名は、列に並ぶ保護者の方々に『地蔵盆に関するアンケート調査』への協力を依頼して回りました。
じっとしていても汗が噴き出す暑さとなったこの日。その暑さをものともせず、時間を追うごとに増え続ける人。列の後半は日よけのない場所だったため、学生も汗だくになりながら、訪れる人たちに一生懸命声をかけていました。


炎天下のなか、懸命に調査に取り組んだ学生
ときに断られることもありましたが、多くの方々が快く引き受けてくださり、学生もモチベーションを持って臨めた様子。過去最高を更新し続ける今年の猛暑。数時間にわたる炎天下での調査は大変だったと思いますが、学生は暑さを忘れ、懸命に調査に取り組んでいました。
8月24日(日) 一の谷・潮音寺地蔵盆へのインタビュー調査

翌日には、須磨区一の谷にある潮音寺にて、23日(土)に地蔵盆を終えられたご住職へインタビュー調査を実施しました。
1週間の調査経験で掴んだインタビューのコツ
約1週間の調査を経て、インタビューのコツもつかめてきた学生たち。
お寺の地蔵盆が地域に果たす役割、地蔵盆の継続の工夫等の課題を明らかにするために、ご住職の回答を踏まえたうえで次の質問を繰り出すことができていました。
『社会調査演習Ⅱ』で調査内容を分析・解釈
今回の調査内容は、後期からの『社会調査演習Ⅱ』で分析・解釈し、報告書を作成。調査対象となった方々にフィードバックする予定です。
『社会調査演習Ⅰ・Ⅱ』を含む社会調査士資格認定科目の取得により、『社会調査士※』の資格取得が可能となります。
※ インタビュー調査やアンケート調査の方法を学び、統計や世論調査の結果を検討するなど、社会調査の現場で必要な能力を持った『社会調査』の専門家