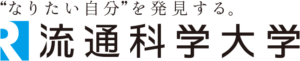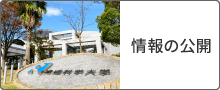支援の輪を広げるために。『ミャンマー地震支援シンポジウム』に本学留学生5名が登壇
公開日:2025年10月8日

今年3月28日、ミャンマー中部を襲ったマグニチュード7.7の大地震。多くの犠牲者と被害を出したこの大地震を受け、大学コンソーシアムひょうご神戸が“支援の輪を広げる”ために『ミャンマー地震支援シンポジウム』を企画。10月3日(金)、本学にて実施されました。
詳細▶ https://consortium-hyogo.jp/myanmar/
『ミャンマーの「今」を知る』をテーマに留学生5名がプレゼン
『MYANMAR 震災から半年を振り返る』と題して行われた本シンポジウム。
『ミャンマーという国の歴史・文化・社会状況を知り、ミャンマー地震による被害とその現状を理解し、地震被害を“自分ごと”として考え、行動につなげることを目的としています。
本学のミャンマー人留学生5名が登壇したのは、神戸市外国語大学国際関係学科・中嶋圭介准教授をファシリテーターに行われた第1部。『ミャンマーの「今」を知る』をテーマに、2グループに分かれてプレゼンテーションしました。
日本で学んだこと、これからやりたいこと
最初に登壇したのは、プ― プイン キー ピューさんとリン ミャッ モン ウーさん(ともに商学部経営学科2年)。まず、ミャンマーという国の言語や宗教、民族、代表的なお祭りなどについて紹介しました。続いて、ミャンマーの人たちがどういった国に留学しているのか、また自分たちがなぜ日本に留学したのか、その理由について説明。日本に留学して感じたミャンマーとの大きな違い、これまで日本で学んだこと、これからやりたいことなどについて、それぞれの思いを話しました。


ミャンマーの現状と、神戸の震災から学ぶ復興への道
次に、チョー ジン ハンさん(商学部経営学科2年)、スー ヤダナー キョウさん・ピェー ピェー テー カインさん(ともに人間社会学部観光学科2年)の3名が、『地震の現状と、より良い復興に向けて』をテーマにプレゼンテーション。
母国ではどのような被害を受け、生活がどう変わったのか。ミャンマーの現状について伝えました。また、重要文化財の被害をはじめ、地震による観光産業への影響についても触れた3名。そのうえで、『神戸港震災メモリアルパーク』や『神戸ルミナリエ』を例に、ミャンマーでも神戸のように『震災から学ぶ観光』が可能ではないか、と未来への希望を力強く語りました。
日本からミャンマーへ。支援活動を継続中
本学では、約100名のミャンマーからの留学生が学んでいます。
母国での大地震を受け、さまざまな思いを抱えながら、この半年間を過ごしてきました。そのなかでも、遠く離れた地からできることを考え、学内イベントでの募金など、継続的な支援活動を行っています。
留学生たちの活動を見かけた際は、ぜひお気持ちを寄せていただけると嬉しいです。

“自分ごと”として考える。それが支援の最初の一歩
留学生たちのプレゼンテーションの後、国連移住機関IOM駐ミャンマー代表・望月大平氏が、Zoomを通して現地の状況をレポートされました。報告の最後に、「ミャンマーに対する世界の注目度が下がってきている」と話した望月氏。地震発生からまだ半年。まだまだ継続的な支援が必要な状況です。参加された皆さまにとって、改めてミャンマーの人々に心を寄せ、『自分にできること』を考える貴重な機会となりました。
この日のプレゼンテーションで、震災を経験した神戸の街から復興のヒントを得て、母国の未来を力強く語った留学生たち。その思いが、ミャンマーの復興につながっていくことを、心から願っています。