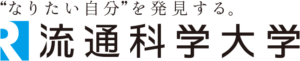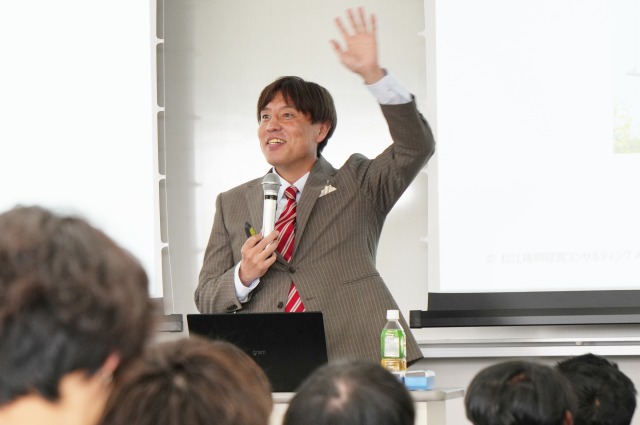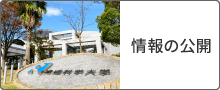『社会調査演習Ⅰ』で神戸市西部地域の地蔵盆・地蔵祭を調査。行事継承と地域活性化を考える
公開日:2024年9月27日

本学の人間社会学部には、3年生から履修することができる『社会調査演習Ⅰ・Ⅱ』という科目があります。
人々の消費の場であり生活空間でもある商店街で執り行われる催事、特に『地蔵祭・地蔵盆』を対象に社会調査を行うもの。催事の実施、継続方法や諸問題に関する調査を行い、社会調査を立案・実践する力を身につけ、一連の統計調査法の手順・技法を実践的に修得することを目的としています。
今年度も、『神戸市西部地域の地蔵盆・地蔵祭の可能性から考える行事継承と地域活性化の要素』をテーマに、社会調査を実施しています。
7月6日(土) 『地蔵盆・地蔵祭』について事前調査

7月6日(土)、本講義を受講する学生3名が、須磨寺前および新長田を中心に事前調査を実施しました。
この日は新長田駅からスタート。担当教員である人間社会学部心理社会学科・栗田真樹教授と桑原桃音准教授とともに、駅前に掲示された地図を見ながらルートを確認。新長田1番街商店街と大正筋商店街それぞれの地蔵盆開催地を目指しました。

栗田教授や桑原准教授からの説明を聞きながら、商店街を歩く学生たち。目的の地蔵尊にたどり着くと、それぞれ写真を撮ったり、傍らにある説明を読みメモを取ったり。また、ときには地蔵盆の提灯を掲げている店舗を見つけ、お話を聞く場面も。


新長田での最後の目的地、智慧地蔵尊を経て、須磨寺へ。須磨寺では、桜寿院から親子地蔵までを1周した後、学生それぞれが気になる場所を約1時間かけて調査しました。そして、須磨寺駅前商店街を観察しながら、駅前の地蔵尊へ。ここで毎年行われている地蔵盆について、桑原准教授から説明を受けました。


じりじりと焼けつくような真夏日となったこの日。炎天下のなか、学生たちは流れ落ちる汗をぬぐいながら歩きまわり、調査に励んでいました。次回は、8月23日(金)に新長田商店街、須磨寺周辺にて本調査を実施します。
8月23日(金) 『須磨寺』『新長田駅周辺』地蔵盆にて本調査

7月の事前調査を経て、8月23日(金)に須磨寺および新長田駅周辺で行われた地蔵盆で、本調査を行いました。
この日は、須磨寺チーム・新長田チームに分かれて調査を行った学生たち。須磨寺チームの学生は、桑原准教授とともに15時の地蔵盆開始までお菓子の準備などを手伝いました。その間にも、境内には待ちきれないとばかりに多くの子どもたちの姿が。そして15時。地蔵盆がはじまると、テント前には長蛇の列ができ、学生も汗をぬぐいながら笑顔で子どもたちにお菓子を手渡していました。




用意したお菓子をすべて配り終えた後は、須磨寺の副住職の方にインタビュー。限られた時間ではありましたが、地蔵盆についてのお話をいろいろとお聞きしました。
一方、新長田チームの学生は、調査を行う3~4カ所をピックアップすることからスタート。この地域は、複数箇所で地蔵盆が開催されていて、あちこちに提灯が飾りつけられていました。まず栗田教授とともに、開始が一番早い長福寺へ向かった学生。地蔵盆開始まで住職の方にインタビューし、さまざまなお話しをお聞きしました。

じっとしていても汗が噴き出すような暑さのなか、ピックアップした地蔵盆を目指して、広範囲を移動。それぞれの地蔵盆の特徴や気づいたことをメモしたり、積極的に主催者の方々に声をかけて話を聞いたり。猛暑のなか、何時間もかけて調査を行いました。


アンケート調査を実施した昨年度とは違い、『観察』のみとなった今回。そのなかでも、学生たちは、それぞれ自分なりに考えて調査に取り組んでいました。今回の調査内容は、後期からの『社会調査演習Ⅱ』で分析・解釈し、報告書を作成していきます。
この『社会調査演習Ⅰ・Ⅱ』を含む社会調査士資格認定科目の単位取得により、『社会調査士※』の資格取得が可能となります。
※ インタビュー調査やアンケート調査の方法を学び、統計や世論調査の結果を検討するなど、社会調査の現場で必要な能力を持った『社会調査』の専門家